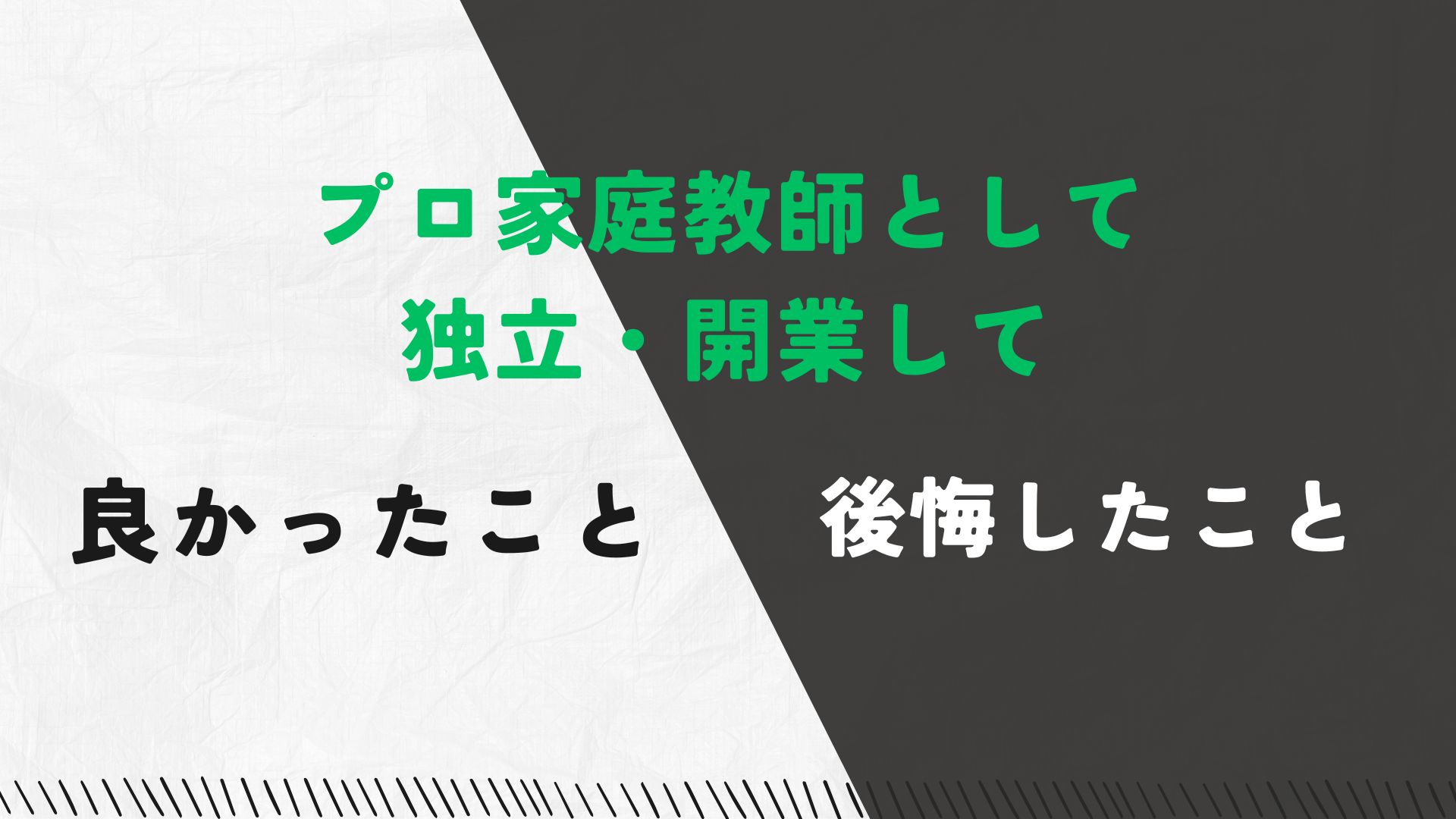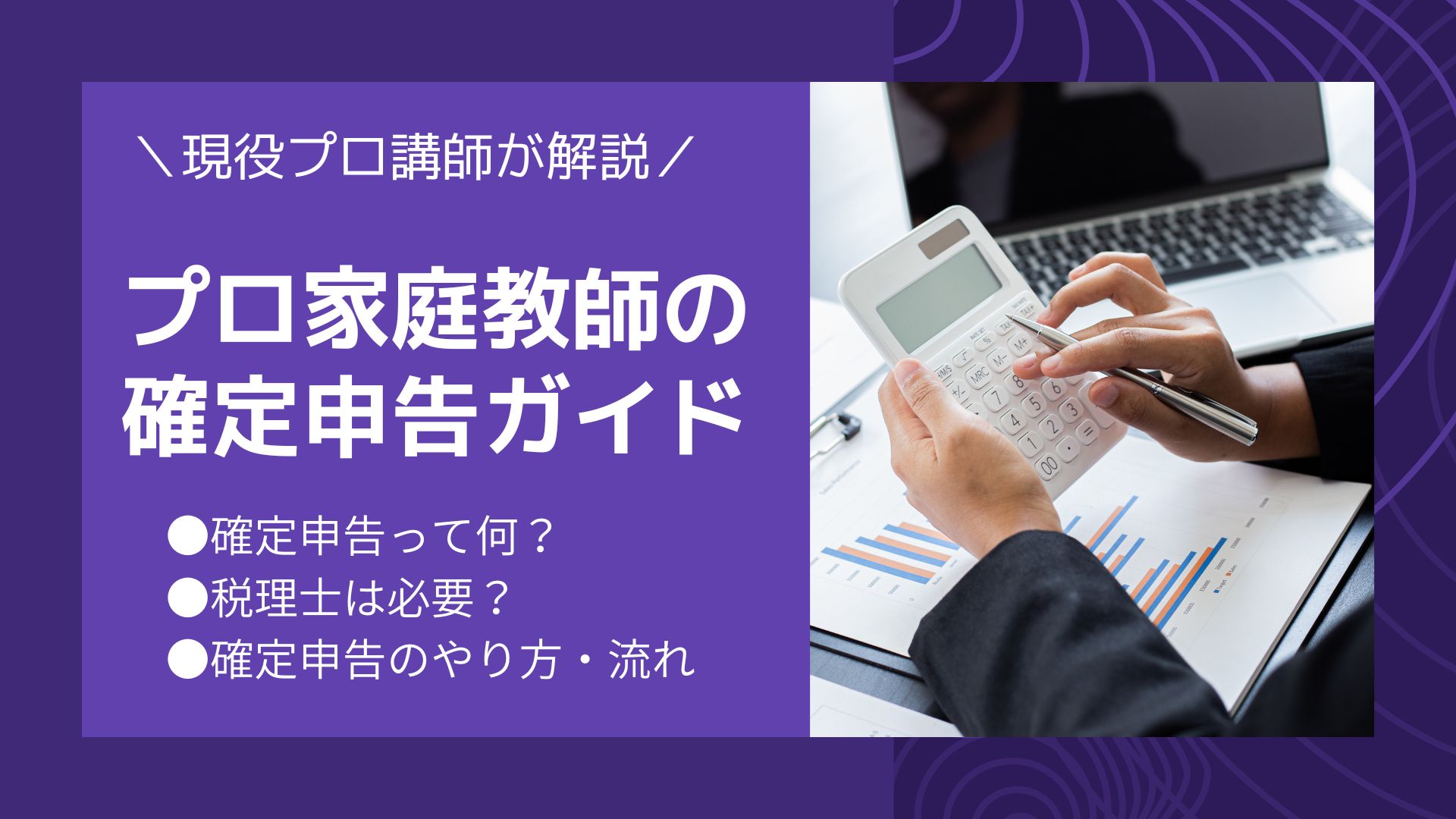こんにちは、プロ家庭教師のひかるです。
正社員の塾講師を辞めて、独立するときに、何から始めたらいいのかわかりませんでした。
同じように、悩んでいる人も多いのではないでしょうか?
私が個人事業主として開業するために参考にした本が、こちら↓
見田村元宣さん・内海正人さん『フリーランスの教科書』
その名の通り、フリーランスになるための基礎知識を学べる新書です。
読んだ率直な感想は、

読んでよかった…
です。
自営業(個人事業主・フリーランス)になると、正社員時代には会社がやってくれていたことを自分でやらなければなりません。
独立するときに、自営業の隅々まで知っておく必要はありませんが、ある程度は知的武装しておいた方がスムーズに開業できます。
- 会社員という生き方に不安を感じている
- やりたいことが見つかった
- 独立・開業しようと思っている
- でも何から始めたらいいのかわからない
という人に、おすすめの本です。
『フリーランスの教科書』はこんな本
この本をひとことでまとめると、
独立・開業するときに知っておきたい知識がまとまっている本
です。
書いたのは、税理士の見田村元宣さんと、社会保険労務士の内海正人さん。
ただ、堅苦しい実務書ではなく、読みやすいストーリー形式になっています。
フリーランスになりたての「僕」が、税務と社会保険のプロから、自営業のノウハウを教えてもらうという形で解説が進んでいきます。
目次・章立てはこんな感じ↓
『フリーランスの教科書』より引用
- 契約とギャラ交渉
- 税金と確定申告
- 保険と年金
- 法人化
フリーランスは、雇用された会社員ではありません。
基本的に、案件ごとに「業務委託」として仕事を請け負う立場です。
会社員の場合には、部署ごとに役割分担されていて、会社が所得税や社会保険料を天引きし、年末調整までしてくれていました。
一方、フリーランスの場合には、業務委託契約、ギャラ交渉、確定申告、納税などを自分でしなければなりません。

ややこしそうやな…
と思い、独立・開業に、一歩踏み出せない人も多いのではないでしょうか。
この本を通して、自営業(個人事業主・フリーランス)がどう生き方なのか、どうやって生きていけばいいのか学ぶことができます。
『フリーランスの教科書』のインプット3つ
実際に読んで、プロ家庭教師として独立・開業するときに勉強になったことを、いくつか備忘録がわりにまとめておきます。
『フリーランスの教科書』を読んで、インプットしたことは、
- 自由の裏返しは「自己責任」
- 確定申告にビビらない
- 自分の身は自分で守る(保険)
の主に3点です。
自由の裏返しは自己責任
自営業になると、基本的には上司も部下もいません。
決められた出勤時間も場所も、仕事内容もありません。
何をするにも、自由に仕事をすることができます。
一方で、自営業のデメリットは「自己責任」です。
「自由」と「自己責任」は表裏一体ですね。
『フリーランスの教科書』では、次のように書かれています。
一見いいようだけど、自分で自分をマネジメントしないといけないことがわかった。(中略)フリーランスはいわば「小さな法人」であることも教えてもらった。営業部も広報部も経理も社長も全部、僕なんだ。
『フリーランスの教科書』より引用
つまり、仕事をするのも、サボるのも、儲けるのも、赤字になるのも自分次第ということです。
私が個人事業主になったときに、かつての同僚に「正社員になれないんですね…」と憐みの言葉をかけられました。
でも、会社員と自営業って、どちらが良くて、どちらが悪いというものではありません。
どちらにもメリット・デメリットがあり、どういう働き方・生き方を選ぶかという価値観の問題ですね。
別のブログで、プロ家庭教師として開業したメリット・デメリットをまとめた記事があります↓
『フリーランスの教科書』を読んで、独立・開業する心構えも学べました。
確定申告にビビらない
個人事業主になる前に、1番心配していたのが「確定申告」でした。
ぼんやりと「自営業になると確定申告ってやつをして、税金を自分で払わないとあかんのやな」くらいんの認識でした。

確定申告でミスッたら脱税で逮捕されるんかな…
なんて思ってビビっていました。
『フリーランスの教科書』を読んで、確定申告が具体的に何をすればいいものなのか知れました。
お化けの正体がわかって安心した感じでした(笑)
『フリーランスの教科書』より引用
- 税金は「事業所得ー控除」に対してかかる
- 経費や各種控除が多いほど税額は減る!
きちんと領収書・レシートを残しておき、「経費」として計上することで税額をおさえることができます。
よくレジで「領収書ください」と言っている人がいるのは、そのためなんですね。
1年間の収益から、その収益を稼ぐためにかかった必要経費などを差し引き、所得税・消費税などの税額を計算するのが「確定申告」ってわけです。
また、確定申告には「青色申告」と「白色申告」があります。
「青色申告」には、いくつかのメリットがあります。
(青色申告のメリットは)まず、65万円の『青色申告特別控除』が認められていること。事業所得から65万円を引けます。つまり、経費が65万円多く認められたのと同じなんですね。
『フリーランスの教科書』より引用
要するに、「節税」になるってわけです。
そのためには「青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出しておかなければなりません。
「開業届」といっしょに提出しておけばOKです。

この本を読まないと、そんなこと知りませんでした
また、本の最後に「確定申告の書き方ガイド」をつけてくれています。
その見本通りに確定申告の書類を作ればOKなのです。
ただ、手書き&手計算はさすがに面倒くさすぎますし、帳簿をつけるための「複式簿記」の知識も私にはありません…
ですので、青色申告ソフトをつかって、確定申告することにしました。
※別サイトで、プロ家庭教師の確定申告の流れをまとめています↓
「確定申告ソフトに頼った方が手っ取り早い」とわかっただけでも、本を読んだ価値がありました。
お金の出入りがシンプルな家庭教師業でさえ手書き・手計算は面倒なので、他の業種の方はなおさら会計ソフトを使った方がいいと思います。
確定申告ソフトを使えば、複式簿記の知識がなくても、家計簿に入力する感覚で帳簿を作り、確定申告をすることができます。

確定申告自体が、めんどくさいことには変わりないやん
自分の身は自分で守る(保険)
「会社員って会社に守られていたんやな」と実感するのが、社会保険です。
私もサラリーマン時代には、そんな実感はありませんでした。
むしろ、給与からかなりの額の保険料や所得税が天引きされて、手取りが減っていることに不満を感じていたくらいです。
実際には、『フリーランスの教科書』によると、会社側が会社員の社会保険料をかなり負担してくれています。
サラリーマンの場合には、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金という4つの社会保険に加入しています。ところが、最初に説明したように、フリーランスは労働者ではなく、個人事業主だから、労災保険と雇用保険には加入できません。保険は『健康保険』と『国民年金』の2つだけになりますね。(中略)
『フリーランスの教科書』より引用
(サラリーマンに場合)雇用保険は会社側が半分以上、健康保険と厚生年金は会社側が半分払ってくれるし、労災保険に至っては会社が全額負担ですからね
実際、自営業になって、健康保険と国民年金の納付書・振込用紙が届いてビビりました…
「そもそも社会保険料が高すぎる!」というのはもちろんですが、個人事業主はすべて自己負担だというのは、開業する前に知っておいた方がいいことです。
また、会社に勤めていると、毎年健康診断があります。
でも、独立すると、健康も自己責任です。
労災もないので、自分が働けなくなると収入がゼロになる可能性があります。
市の健診・人間ドックを受診したり、運動したりして、会社員時代以上に健康にも気を配らなければなりません。

と言いつつ、全然運動してへんわ…
まとめ:『フリーランスの教科書』独立開業するなら読んでおきたい1冊【書評13】
フリーランスとして独立することは、なんだか怖いことのように感じるかもしれません。
でも、いざ自営業になってしまえば、ただ日々の仕事に取り組むだけです。
『フリーランスの教科書』を読むことで知識を身につけ、開業するときの不安を解消することができました。
また、自分が自営業に向いているかを判断するきっかけにもなります。
- 会社員という生き方に不安を感じている
- やりたいことが見つかった
- 独立・開業しようと思っている
- でも何から始めたらいいのかわからない
という人は読んでみてはいかがでしょうか?